都議会・決算特別委員会の第二分科会(福祉、保健医療分野)にて質疑を行いました。
内閣府の令和4年度調査によれば、全国の15歳から64歳までのひきこもり人口は146万人に上ります。
特に深刻なのは、中高年層が約85万人と若年層の約61万人を上回り、長期化・高齢化が進行していること。
高齢の親と中高年のひきこもりの子という「8050問題」も顕在化しています。
ひきこもりのご家族や元当事者の方々からご意見を伺い、この問題の深刻さを実感しました。
ひきこもりは特別なことではなく、誰にでも起こりうること。
適切な支援につながることで、一歩を踏み出すことができます。
実際に、当事者や支援団体の方々からのヒアリングをもとに、決算特別委員会で質疑しました。
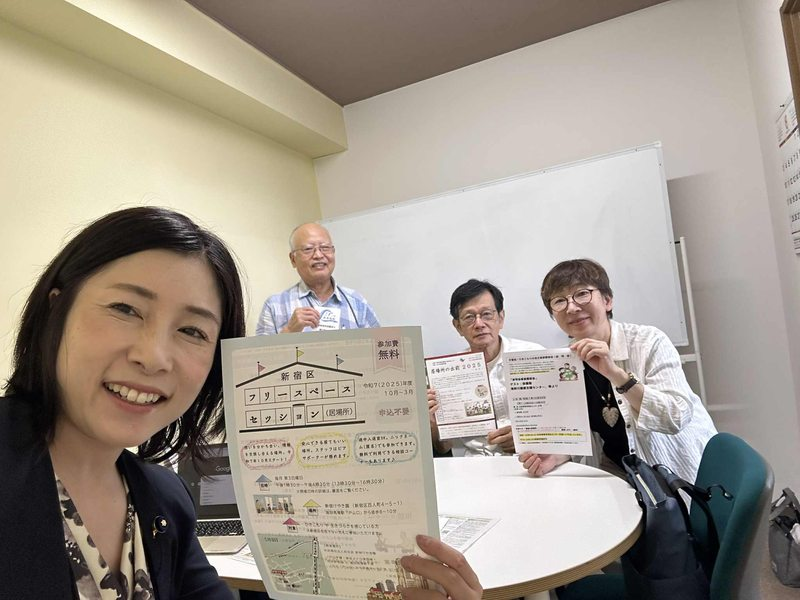
—
🟩都が展開する積極的な広報活動
🖐️質問1:令和6年度の広報活動実績は?
👨答弁
都では、多様な媒体を活用した積極的な広報活動を展開
📺動画広告
YouTube広告:約162万回再生
トレインチャンネルで配信
🏪店舗での周知
都内コンビニ約1,300店舗
薬局約100店舗で動画配信
🚇交通広告
都営地下鉄全線で約1,600枚のドアステッカー広告
📄紙媒体
ポスター約7,400部を薬局・図書館に配布
リーフレット約30,000部を関係機関に配布

📈広報活動が相談件数増加に直結
🖐️質問2:相談実績の推移は?
👨答弁
令和6年度「東京都ひきこもりサポートネット」の相談実績
電話相談:4,271件(前年比105%)
メール相談:545件(前年比97%)
来所相談:130件(前年比125%)
訪問相談新規受付:25件(前年比156%)
🖐️質問3:令和7年1月の集中広報後の変化は?
👨答弁
令和7年1月、長期休み明けに集中的に広報を実施
インターネット・電車・コンビニ・新聞など多様な媒体を活用
対象者に応じた情報発信
都民向け
→「ひきこもりへの正しい理解」
当事者・家族向け
→「相談窓口の周知」
結果
電話相談:312件(前月比111%)
メール相談:45件(前月比132%)
集中広報が即座に相談増につながりました。

🤝支援につなげる取組
🖐️質問4:支援機関へのつなぎ実績は?
👨答弁
令和6年度の紹介件数:1,662件
サポートネットでは
・継続的な相談対応
・区市町村の相談窓口を紹介
・民間支援団体等を紹介
・紹介後も要望があれば継続支援
一人ひとりの状況に即した支援を実施しています。

🔲当事者の声を活かす
🖐️質問5
満足度や評価をどう活かしているか?
👨答弁
講演会や合同説明相談会でのアンケート調査を実施。
令和6年度の評価
「ひきこもりへの理解が深まった」
「相談したい支援団体とつながることができた」
概ね9割の方から好評。
アンケートで「ひきこもり当事者の話を聞きたい」との要望 → 令和7年度は元ひきこもり当事者が出演
利用者の声を着実に事業改善に活かしています。

🔲令和7年度の新たな取組
🖐️質問6:今後の広報強化策は?
👨答弁
ひきこもり支援協議会(元ひきこもり当事者やご家族等が参画)から 「人目を気にせず手に取りやすいサイズの有用性」に関する意見
新たな取組
\名刺サイズのポケット相談メモを作成/
人目を気にせず手に取れる
→ 真に情報が必要な方に届く工夫
デザインも内容もとても良いです
✨
北区でも図書館、生活福祉課の相談窓口、社会福祉協議会、健康支援センター、包括地域センターに設置予定💡
🌸一歩踏み出せる社会へ
人目を気にせず手に取りやすい名刺サイズのポケット相談メモという、当事者の心理に配慮した新たな取組を高く評価します。
ひきこもり支援協議会の意見も取り入れながら、真に情報が必要な方に届く工夫をされている点も重要です。
146万人という深刻な状況にあるひきこもりの方々とご家族が、必要な支援に確実につながることができるよう、求めました。
ひきこもりは特別なことではありません。 誰もが安心して相談でき、一歩を踏み出せる東京・北区を目指します。
🍀お悩みの方は🍀
🔍東京ひきこもりサポートネット

--------------------------------------------------------------------------------------------
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
にほんブログ村に参加中です。もしよろしければクリックして応援お願いします。
にほんブログ村
