令和7年10月3日、総務委員会理事として総務委員会にて質疑を行いました。
都は、子どもを権利の主体として尊重し、子どもの最善の利益を第一に考える「チルドレンファーストの社会」の実現を目指しています。
その具体的な道筋を示すものとして、「チルドレンファーストの社会の実現に向けた子供政策強化の方針2025」が策定されました。
子ども政策を進めるにあたり、当事者である子供の声を聴き、政策に反映することは、子供の権利を保障する上で極めて重要です。
子どもは保護の対象であるだけでなく、自らの意見を表明し、社会に参画する権利を有する主体です。
「政策強化の方針2025」では、都が18,000人もの子どもの声を聴いたと記されており、子どもの意見聴取に積極的に取り組んでいる姿勢が示されています。
しかし、数の多さだけでなく、多様性の確保が求められます。
経済的に困難な状況にある子ども、不登校の子ども、児童養護施設で暮らす子ども、外国にルーツを持つ子ども、など、様々な環境下に置かれた子どもの意見を都がしっかりと把握することが重要です。
そこで、「チルドレンファーストの社会の実現に向けた子供政策強化の方針2025」における子どもの意見聴取の取組について、質問しました。
目次
⭐️今回の質疑で
【都は、地域レベルで更に子どもの声を聴く取組を広げるため、区市町村への総合的な支援を検討している】
ことが分かりました。
(まだフワっとしてますが…)
現場の声として、学校の校則、ルールなど子ども達の声を聴いて作成したとは言い難い内容も散見されるなか、しっかりと取り組みを進めていきたいと思います。

—
Q1: 都における子どもの意見聴取の取組状況は?
都における子どもの意見聴取の取組状況、中でも今年度の取組の工夫について伺います。
A1(都答弁)
○都は、子どもの声や思いを反映した子ども政策を推進するため、「子供の居場所におけるヒアリング」や「こども都庁モニター」、「SNSアンケート」など多様な手法を活用し、幅広い子どもの意見を聴き、政策に反映する取組を実施
○これらに加えて、各局施策をテーマに子どもの生の声やニーズを把握する「こどもワークショップ」や、子ども自らが子供政策について議論・提案する「中高生政策決定参画プロジェクト」など、子どもが都政に直接参画できる先駆的な取組も進めている
○今年度の取組の工夫について、「子供の居場所におけるヒアリング」において、困難な状況にある子供の意見を重点的にヒアリングし、声をあげにくい子どもの意見の把握に努めている
—
様々な環境下にある子ども、特に不登校、児童養護施設入所者、外国ルーツなど声をあげにくい子どもの声に耳を傾けることは重要です。
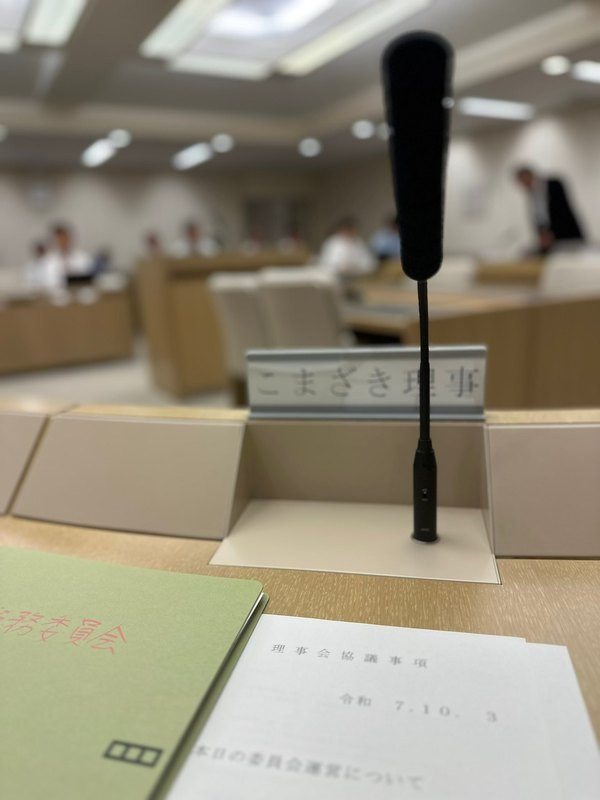
Q2: 声を上げにくい子どもへの配慮はどうしているのか?
声を上げにくい子どもへの意見聴取は、どのように行っているのか、自分の思いを表現することが苦手な子どもや傷つきやすい状況の子供への配慮についても併せて伺います。
A2(都答弁)
○「子供の居場所におけるヒアリング」では、子供が日常を過ごす多様な居場所へ、子供との対話経験が豊富なファシリテーターが訪問し、一人ひとりの実情に寄り添ったきめ細かなヒアリングを約500名の子供に対して実施
○今年度は、子供食堂、日本語教室、フリースクール、児童養護施設、放課後等デイサービスを重点施設として、声をあげにくい子供の声や思いを丁寧に聴取
○ヒアリングに当たっては、子供が緊張せずリラックスできる雰囲気づくりに努めるとともに、年齢・発達段階に応じたファシリテートを行うなど、子供が安心して本音を話しやすい環境づくりに取り組んでいる
○また、発言者が特定されないよう匿名性を担保するとともに、話したくないことを無理に聴き出さないなど、ヒアリングを通じて子供に不利益が生じることのないよう、配慮を徹底
—
声をあげにくい子どもの声にも寄り添い丁寧に聴きとるなど、様々な工夫を凝らして子どもの意見を聴いていることが分かりました。
意見を述べてくれた子供たちに自分の意見がどのように施策に反映されたのか伝えていくことも重要です。

Q3: 子供たちへのフィードバックはどうしているのか?
意見の反映状況について、反映されなかった意見も含めて子供たちへフィードバックすべきと考えますが、見解を伺います。
A3(都答弁)
○意見聴取の取組を通じて寄せられた子供の意見や、その反映状況については、子供の成長・発達段階に応じて分かりやすくまとめた冊子やリーフレットを作成、参加した子供たちにフィードバック
○施策に反映した意見だけでなく、反映に至らなかった声や思いも丁寧に受け止め、フィードバック資料には様々な子供の声を幅広く掲載
○こうしたフィードバックを通じて、子供の社会への参画意欲や自己肯定感の向上につなげている
—
子どもの年代に合わせて丁寧にフィードバックしていることが分かりました。
一方、区市町村においても、子どもの意見を聴き、ニーズを踏まえた取組を進めていくことが重要です。

Q4: 区市町村への展開はどうするのか?
こうした仕組みを区市町村でも取り入れていくことが必要だと考えますが、見解を伺います。
A4(都答弁)
○子供にとって身近な存在である区市町村が、様々な環境下にある子供の意見を聴くとともに、施策への反映状況等をフィードバックすることは重要
○今後、都は、地域レベルで更に子供の声を聴く取組を広げていくため、区市町村への総合的な支援を検討
🔲「聴く」だけでなく「反映する」ことが重要
子どもの声を政策に反映する取組が都全域に広がるよう、しっかりと政策を進めていただくことを期待します。
子どもの声を聴くことは、チルドレンファーストの社会を実現する上での出発点です。しかし、聴くだけでは十分ではありません。
聴いた声を実際の政策にどう反映させるか、実施した政策が子どもたちにとって本当に良いものとなったのか検証すること、
そして政策実施後に改めて子供からもフィードバックを得ることまでが一連のプロセスとして重要だと考えます。
これらを総合的に捉え、子どもの声が都政に生きる取組を進めていただきたいと思います。
例えば、学校の校則やルールは、子供の声を聞くことなく一方的に定められ、理不尽な内容に悩む生徒がいます。
子どもの声を政策に反映する取組が都全域に広がり、真に子供を中心に据えた政策が展開されるよう、
総合的かつ継続的に取り組んでいただくことを求め、質問を終わります。
🟩 チルドレンファーストの社会の実現に向けた子供政策強化の方針2025
https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kodomo-seisaku-kyoka
--------------------------------------------------------------------------------------------
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
にほんブログ村に参加中です。もしよろしければクリックして応援お願いします。
にほんブログ村
